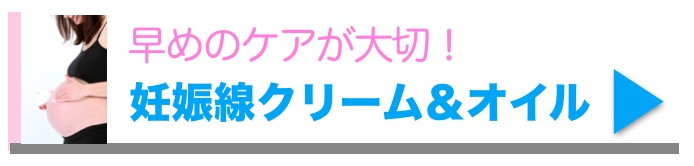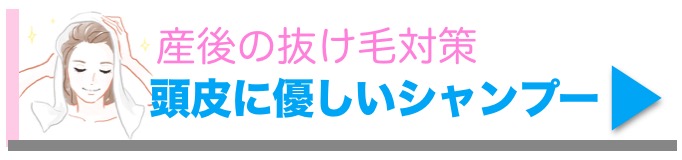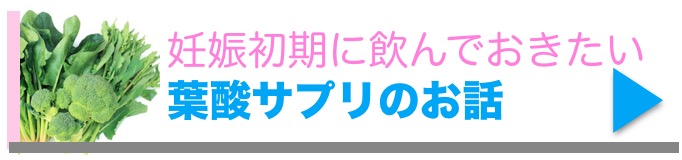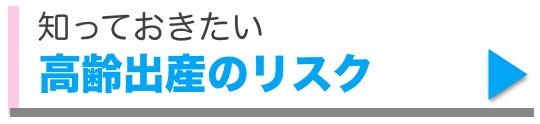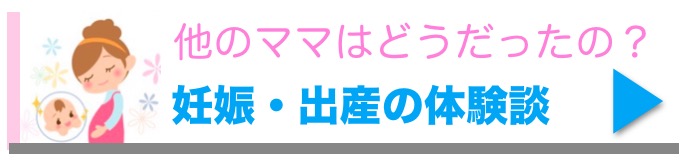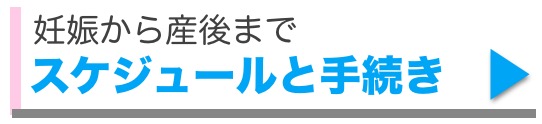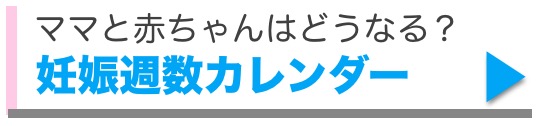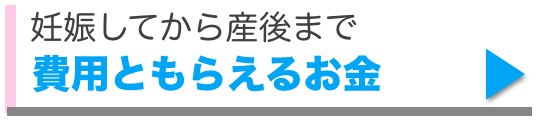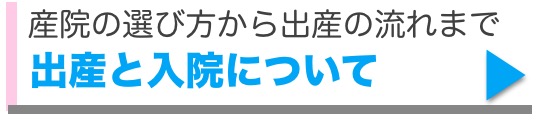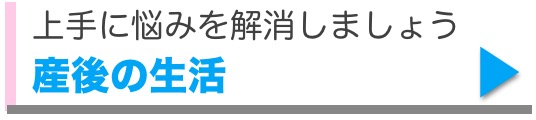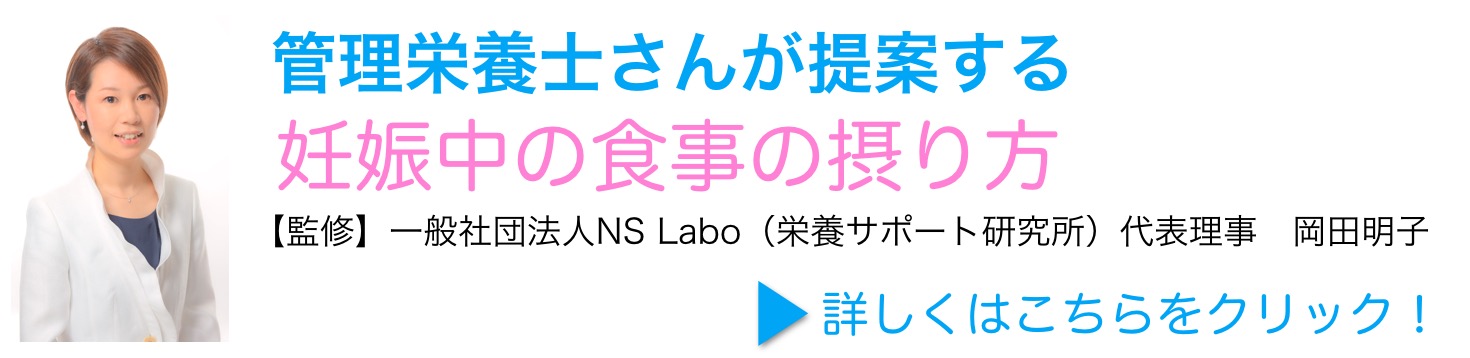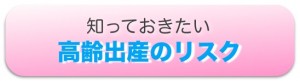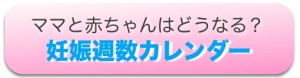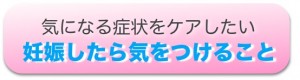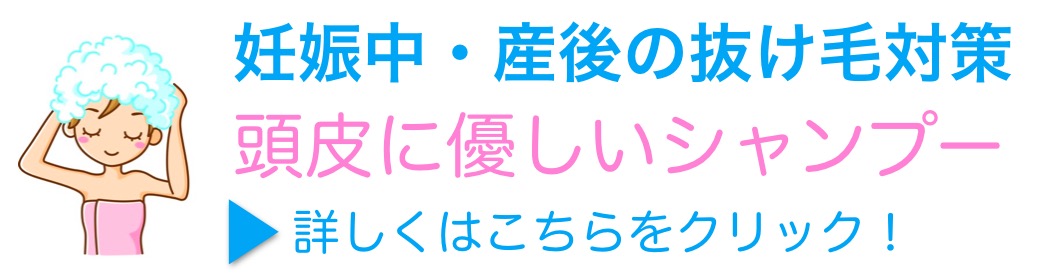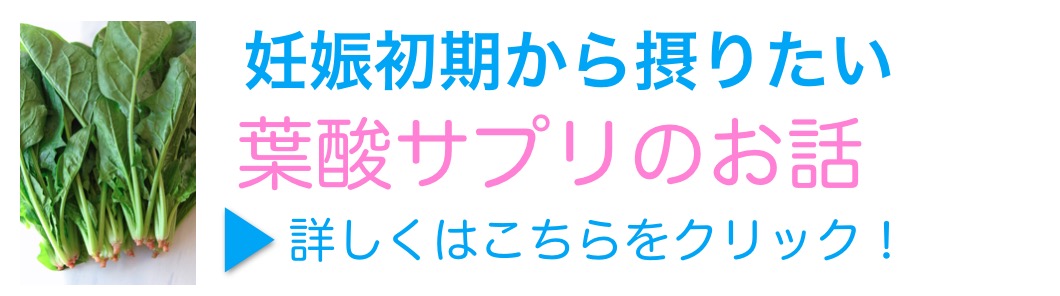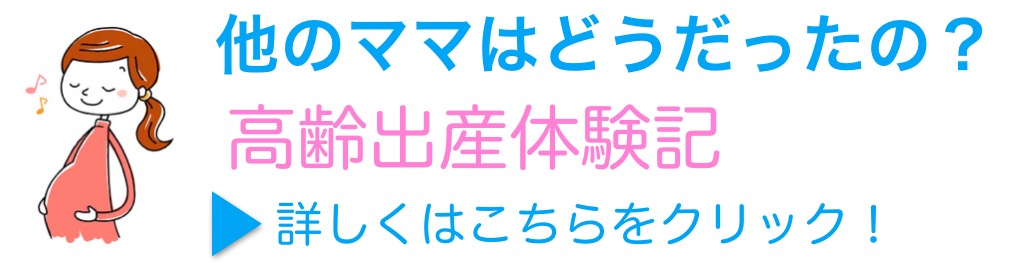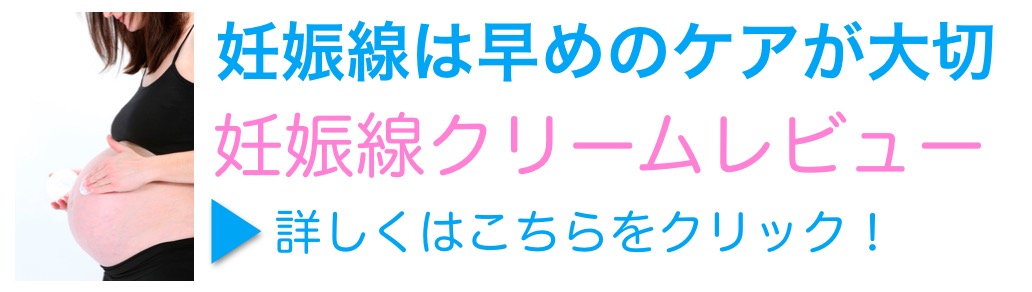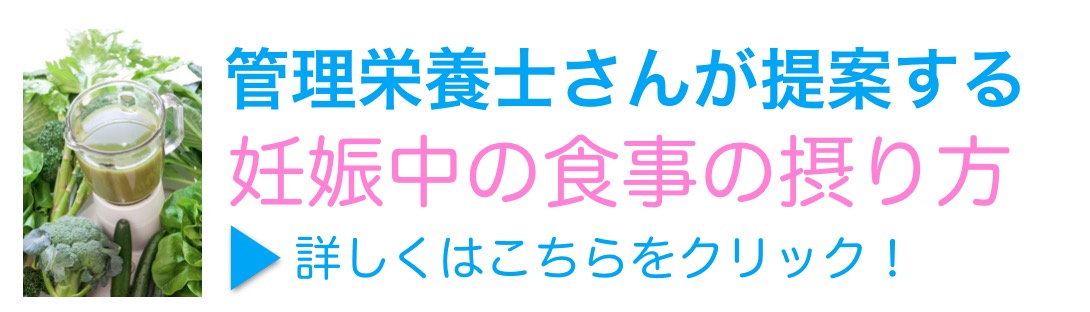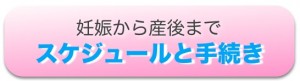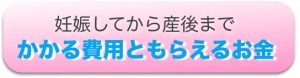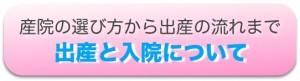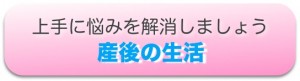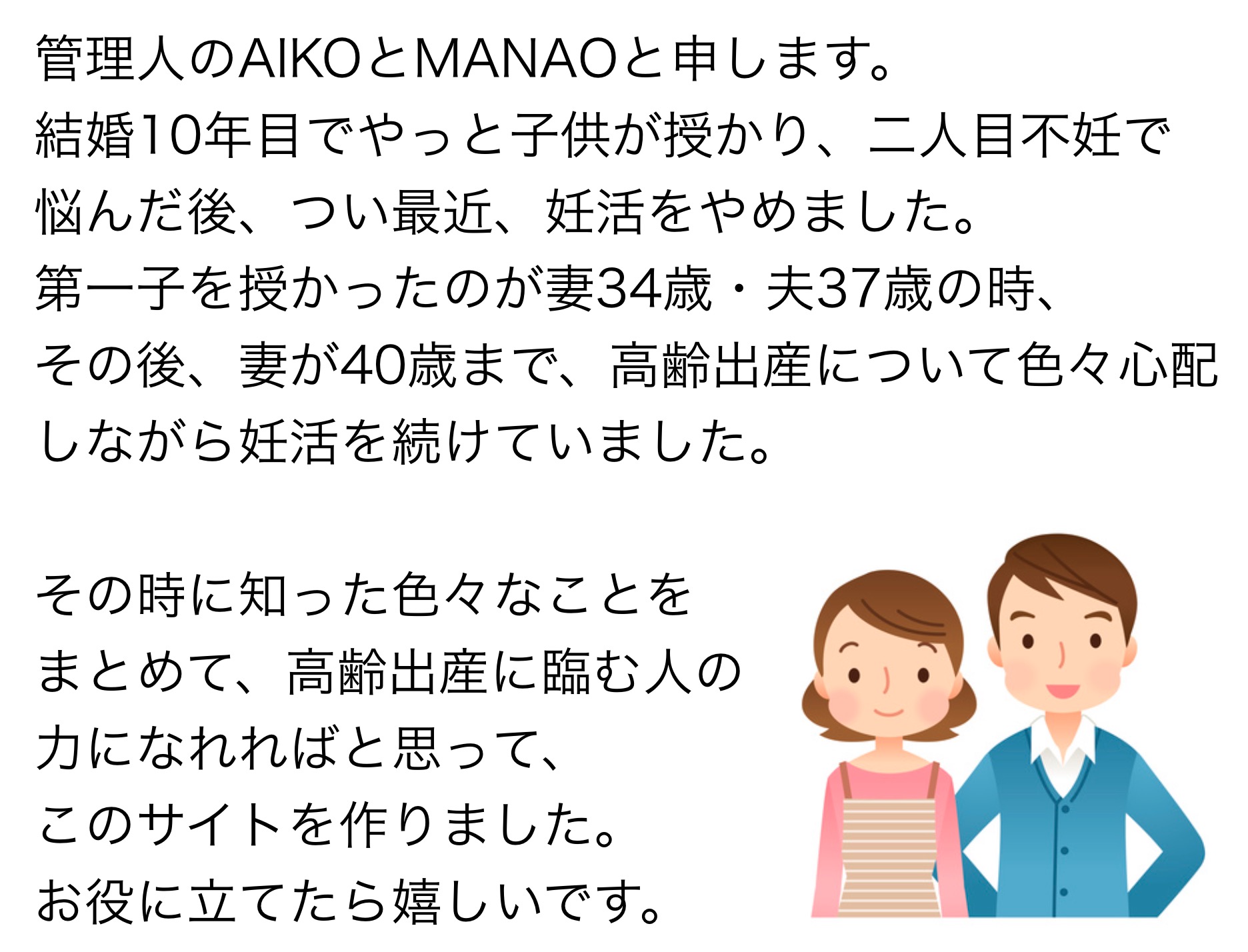妊婦検診の公費負担は自治体によって異なります

妊婦検診は、妊娠したママと赤ちゃんの健康を守るための検診です。
受ける受けないは自由ですが、受けておかないと、重大なトラブルが起こった時に、その発見が遅れてしまいます。
一方で、妊婦検診には健康保険は効きません。
1回あたり5,000円程度、多い時には10,000円以上かかることも。
そこで国では、妊婦検診の公費負担の制度を作っています。
これは、住んでいる区市町村から、妊婦検診の費用を助成してもらえる仕組み。
この記事では、妊婦検診の公費負担がどのくらいもらえるのか?手続きはどうしたらよいのか?について紹介したいと思います。
2. 妊婦検診の公費負担は、自治体によって異なる
– 自治体による助成金額・内容の違い
– 補助券?受診券?助成方法も違うんです
3. 妊婦検診の公費負担を受ける手順は?
– 妊娠確定後にすぐに行うこと
– 妊婦健診の時の流れは?
妊婦検診にかかる費用

妊婦検診の費用は、1回につき5,000円程度、多い時には10,000円を超えることもあります。
厚生労働省からは、この検診を14回受けるように呼びかけられています。
具体的には、以下のような検診スケジュールですね。
- 妊娠23週まで:4週間に一度
- 妊娠24~35週:2週間に一度
- 妊娠36週以降:1週間に一度
出典元:厚生労働省「妊婦健診を受けましょう」より
そのため、妊婦検診は全部で10万円程度かかるのが平均的。
決して少ない金額ではありませんね。
妊婦検診の公費負担は、自治体によって異なる
自治体による助成金額・内容の違い
全部で約10万円かかる妊婦検診に対して、公費負担の制度があります。
これは、在住の自治体が、妊婦検診にかかる費用を助成するもので、自治体によって助成内容や金額にはバラツキがあります。
厚生労働省の調査(平成26年)によると、妊婦検診の公費負担の金額は、全国平均で98,834円。
市町村の公費負担が最も多い岐阜県の117,882円から、最も低い神奈川県の64,319円までかなりの開きがあります。
厚生労働省の資料を元に、公費負担の金額が多い順に、都道府県を並べてみました。
ただし、*マークがついているものは、統計データの明示されていない市町村を除いたデータなので、正しい平均値とは言えません。
あくまでも参考程度に・・・。
| 1 | *青森県 | 118,920 | 25 | 佐賀県 | 98,370円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岐阜県 | 117,882円 | 26 | 岡山県 | 98,297円 |
| 3 | 山口県 | 116,315円 | 27 | 福井県 | 97,590円 |
| 4 | 長野県 | 116,214円 | 28 | 石川県 | 97,414円 |
| 5 | 徳島県 | 113,880円 | 29 | 熊本県 | 96,600円 |
| 6 | 高知県 | 110,380円 | 30 | 和歌山県 | 96,484円 |
| 7 | 福島県 | 110,158円 | 31 | *大分県 | 96,600円 |
| 8 | 香川県 | 109,800円 | 32 | 奈良県 | 95,782円 |
| 9 | 三重県 | 109,590円 | 33 | 栃木県 | 95,000円 |
| 10 | 秋田県 | 108,428円 | 34 | 鳥取県 | 94,756円 |
| 11 | 宮城県 | 108,377円 | 35 | 北海道 | 93,821円 |
| 12 | 愛知県 | 106,725円 | 36 | 群馬県 | 92,920円 |
| 13 | 島根県 | 106,036円 | 37 | 千葉県 | 92,665円 |
| 14 | 新潟県 | 104,848円 | 38 | 岩手県 | 91,620円 |
| 15 | 鹿児島県 | 102,050円 | 39 | 静岡県 | 91,200円 |
| 16 | 宮崎県 | 101,887円 | 40 | 広島県 | 91,184円 |
| 17 | 福岡県 | 101,300円 | 41 | 京都府 | 90,730円 |
| 18 | 埼玉県 | 100,780円 | 42 | 山梨県 | 88,348円 |
| 19 | 滋賀県 | 100,731円 | 43 | 山形県 | 82,790円 |
| 20 | 大阪府 | 100,209円 | 44 | 兵庫県 | 81,927円 |
| 21 | 長崎県 | 100,000円 | 45 | 東京都 | 80,550円 |
| 22 | 富山県 | 99,410円 | 46 | 愛媛県 | 79,400円 |
| 23 | 沖縄県 | 99,100円 | 47 | 神奈川県 | 64,319円 |
| 24 | 茨城県 | 98,451円 |
補助券?受診券?助成方法も違うんです

妊婦検診の助成方法には2種類あります。
- 受診券を配布する方法
- 金額の書いた補助券を配布する方法
の2つです。
受診券の場合は、初めに自治体から14回分の受診券が渡されて、それを妊婦検診の度に持って行くことになります。
会計時に、妊婦検診受診票を受付に渡して、助成対象になっていない検査については自費を払うという感じです。
ただし、無料で受けられる検査項目は自治体によって異なります。
補助券方式の場合は、補助券に金額が書いてあるので、会計の時にそれを受付に渡して、差額分だけ支払うことになります。
こちらも、無料で受けられる上限金額は自治体によって異なります。
厚生労働省の調査によると、平成26年度4月には、
- 受診券方式
全市区町村の84.8%(1,476市区町村) - 補助券方式
全市区町村の15.2.8%(265市区町村)
となっていて、受診券方式の市区町村が多いようですね。
また、受診券方式の市区町村のうち、国が定める標準的な検査項目を全て実施する市区町村は、62.9%(928市区町村)となっています。
妊婦検診の公費負担を受ける手順は?
それでは、妊婦検診の公費負担を受けるのに、どんなことをしていったら良いのか?について詳しく説明したいと思います。
妊娠確定後にすぐに行うこと
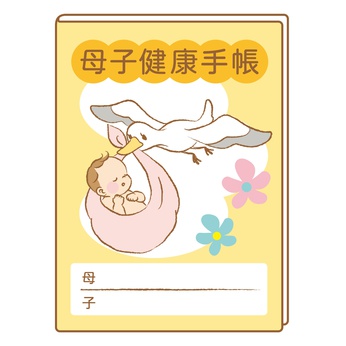
産院で胎児の心拍が確認されると、医師から妊娠届けを出すよう指示が出ます。
そうしたら、住んでいる市区町村の役所に行って妊娠届けを出します。
(自治体によっては、保健所の場合もあり)
妊娠届を提出すると、母子手帳と一緒に、妊婦健診受診券か補助券をもらうことになります。
自治体によっては、超音波検査・歯科検診を上乗せ助成しているところもあるようですね。
妊婦健診の時の流れは?
妊婦検診を受ける時には、受診票(補助券)の記入欄に必要事項を書いて産院に持参します。
すると、会計時に、助成対象になっていない検査の分、もしくは助成額が差し引かれた金額が請求されます。
また、受診票によって、使用できる時期・検査内容が定められているので、医師・看護師に相談するのがベター。
受診票をもらう前に、自己普段で受診した分の払い戻し制度がある自治体もあるので、確認してみてくださいね。
なお、妊婦検診について詳しく知りたい人は、以下の記事を読んでみてくださいね。
かかるお金ともらえるお金(戻る)